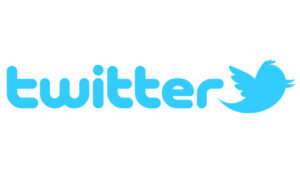まず、相続人を調べる、というと、多くの人は「何で調べるの?家族だったら調べなくてもわかっているよ」と思うでしょう。
でも、家族がわかっていると言っても、法律的には認められません。法律的には、戸籍を収集して、証明することが求められています。
では、どうやって証明するのでしょうか。
この手順は
- 亡くなった人(被相続人と言います)の、出生(生まれた時)から、亡くなった時までの、連続した戸籍を集めます。
このことで、離婚歴があったことを初めて知ったり、家族が聞いたことのない子どもがいることがわかったりすることがあります。養子縁組による子供がいることが分かることもあります。
また、この連続した戸籍集めは大変な労力が要ります。
生まれてから、亡くなるまで一つの戸籍で済む方は、まずいません。
結婚すれば、新たな戸籍になります。
戸籍が、例えば北海道の札幌市にあったことがある場合は、大田区ではとれません。札幌市に郵便で請求しなくてはなりません。
ですから何回も戸籍が代わった場合は、その都度、その市区町村に郵便で請求しなくてはならなくなります。
ですから、大変な労力になります。
戸籍を読むときのポイントですが、
本籍・筆頭者、戸籍の作られた原因、身分事項を読み解きます。
本籍・筆頭者は、戸籍を役所に請求するときに必須です。
戸籍の作られた原因は、その戸籍がいつからいつまでのものなのかを掌握する情報が記載されています。
身分事項は、出生、婚姻、養子縁組などのその人の身分に関する情報です。
また、戸籍を郵送で請求する場合の必要書類は
- 戸籍証明書交付申請書(各市区町村のホームページから入手できる)
- 定額小為替(郵便局で購入、必要な金額を購入して同封)
- 申請者の本人確認資料(運転免許証など)
- 戸籍請求の手掛かりになった資料(手元にある戸籍謄本など)
- 必要な切手を貼った返信用封筒
《相続関係説明図》の作成
誰が法定相続人であるかを示すために作成するもの
相続関係が一目でわかるため、名義変更などの相続手続きで役立ちます。
また、法務局で「法定相続情報一覧図」の作成の基礎資料になりますので、ぜひ作成することをお勧めします。
相続人調査で必要な資料をまとめてみます。
・被相続人(亡くなった方)の住民票除票
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人全員の住民票または戸籍の附票
・法定相続人全員の現在戸籍謄本
・その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本等